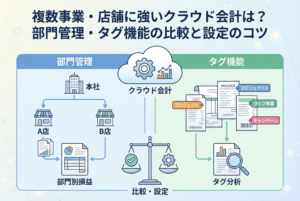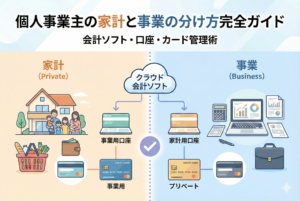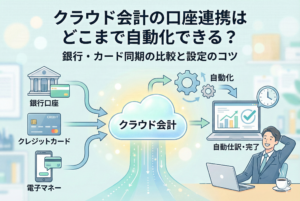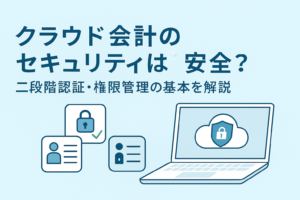会計ソフト選びで迷う経営者・フリーランスの現状
フリーランスや中小企業の経営者にとって、会計ソフトは事業運営の基盤です。
請求書の作成、経費の入力、確定申告や法人決算まで、あらゆる経理業務を効率化してくれる存在だからです。
しかし現在はクラウド会計ソフトの選択肢が増え、**「どれを選べばよいのか分からない」**という声が多く聞かれます。
サポート体制、料金、機能、操作性など、比較するポイントは多岐にわたり、初心者にとっては判断が難しいのが実情です。
会計ソフト選びで失敗しやすいポイント
導入に失敗する典型的なケースは以下の通りです。
- 料金だけで選んで後悔:安価なプランを契約したものの、必要な機能が不足して結局追加費用が発生。
- 操作性が合わない:初心者向けだと思って導入したが、専門用語や複雑な操作で挫折。
- サポート不足:問い合わせ対応が遅く、トラブル時に自力解決を強いられた。
- 事業の成長に対応できない:利用開始時は良かったが、従業員数や取引量が増えた途端に不便になった。
👉 このような失敗を避けるためには、最新のクラウド会計ソフトを比較し、**「自分の事業に最適な一社」**を選ぶことが欠かせません。
結論:2025年におすすめのクラウド会計ソフトランキング
各社の機能・料金・サポート体制を比較した結果、2025年時点でのおすすめランキングは以下の通りです。
🥇 第1位:マネーフォワードクラウド会計
- 金融機関連携数が国内最多クラス。
- 自動仕訳とAI学習で効率化を実現。
- 法人利用や成長段階の事業に強い。
🥈 第2位:freee会計
- 操作画面が直感的で、初心者でも使いやすい。
- 確定申告や青色申告に強く、フリーランスから人気。
- スマホアプリが充実し、モバイル中心の事業者にも好評。
🥉 第3位:弥生会計オンライン
- サポート体制が圧倒的に充実。
- 電話・チャット対応があり、会計知識が少ない人も安心。
- 初年度無料キャンペーンでコスト面も魅力的。
クラウド会計ソフトを比較する4つの基準
クラウド会計ソフトを評価する際には、以下の4つの観点が特に重要です。
- サポート体制:初心者が安心して利用できるか
- 操作性:直感的でわかりやすいか
- 料金:事業規模に応じたコストパフォーマンス
- 機能性:自動化や法令対応など業務効率化に直結するか
この基準で「マネーフォワードクラウド」「freee会計」「弥生会計オンライン」を比較しました。
サポート体制の比較
| ソフト名 | サポートの特徴 |
|---|---|
| マネーフォワードクラウド | チャット・メール中心。ヘルプ記事が豊富。自己解決力が高いユーザー向け。 |
| freee会計 | チャット中心だが、ガイドやコミュニティが活発。利用者同士の情報交換も可能。 |
| 弥生会計オンライン | 電話・チャット・メール対応。初心者でも安心できる充実サポート。 |
👉 初心者は「弥生会計オンライン」が安心。法人利用や経験者はチャット中心でも十分な「マネーフォワード」や「freee」でも問題なし。
操作性の比較
| ソフト名 | 操作性の特徴 |
|---|---|
| マネーフォワードクラウド | 機能が豊富で中小企業でも使いやすいが、初心者は慣れるまで時間が必要。 |
| freee会計 | 質問形式の入力画面が直感的。簿記知識がなくても迷わず入力可能。 |
| 弥生会計オンライン | 従来型の会計ソフトに近く、簿記経験者に馴染みやすい。初心者には「かんたん取引入力」が便利。 |
👉 直感的な使いやすさならfreee会計がトップ。簿記経験者は弥生がスムーズ。
料金の比較
| ソフト名 | 個人向けプラン | 法人向けプラン | 特典・キャンペーン |
|---|---|---|---|
| マネーフォワードクラウド | 月額1,280円〜 | 月額2,980円〜 | 無料トライアルあり |
| freee会計 | 月額1,480円〜 | 月額2,680円〜 | 無料トライアルあり |
| 弥生会計オンライン | 年額8,800円〜 | 年額13,200円〜 | 初年度無料キャンペーン多数 |
👉 コスト重視なら弥生会計オンライン、ランニングコストのバランスなら「マネーフォワード」、利便性を考えると「freee」も選択肢に。
機能性の比較
- マネーフォワードクラウド
- 金融機関連携数が国内最多クラス。
- AI仕訳・経費精算・給与・請求書まで統合可能。
- 成長期の法人に強い。
- freee会計
- スマホアプリが優秀で外出先からも操作可能。
- 青色申告書・確定申告書の自動作成機能に定評。
- 個人事業主・フリーランスに人気。
- 弥生会計オンライン
- 法令改正への対応が迅速。
- 電子帳簿保存法・インボイス制度対応済み。
- サポートに強く初心者が安心して導入可能。
評価まとめ
- 総合力No.1:マネーフォワードクラウド(成長性・自動化)
- 初心者に優しい:freee会計(直感的操作)
- サポート重視:弥生会計オンライン(電話対応あり)
フリーランスの利用事例
事例1:副業ライター(freee会計を導入)
- 導入前の課題
Excelで収支を管理していたが、確定申告期に入力が追いつかず、毎年ギリギリで焦っていた。 - 選んだ理由
freee会計の質問形式の入力が直感的でわかりやすかった。 - 導入後の効果
- 青色申告特別控除65万円をスムーズに適用できた。
- 仕訳の自動化で作業時間が月10時間→月3時間に短縮。
- 「自分一人でも申告できた」という安心感を得られた。
事例2:Webデザイナー(マネーフォワードクラウドを導入)
- 導入前の課題
銀行やクレジットカードの入出金管理を手作業で行っており、記帳ミスが頻発。 - 選んだ理由
連携できる金融機関の数が多く、自動仕訳が優れていると評判だった。 - 導入後の効果
- 自動仕訳の精度が高く、入力ミスが激減。
- 経費精算がスマホアプリから可能になり、外出先でも処理できるようになった。
- 経理に割く時間を制作業務に充てられ、売上増につながった。
法人の利用事例
事例3:ITベンチャー企業(マネーフォワードクラウドを導入)
- 導入前の課題
経理担当者1名に業務が集中し、請求書発行や給与計算に追われていた。 - 選んだ理由
会計・給与・経費精算を一元管理できる点に魅力を感じた。 - 導入後の効果
- 月次決算の締めが15日→5日に短縮。
- 経営会議に最新の会計データを反映できるようになった。
- 経理担当者の負担が軽減され、経営企画業務に時間を使えるようになった。
事例4:老舗小売業(弥生会計オンラインを導入)
- 導入前の課題
デスクトップ型の会計ソフトを利用していたが、担当者が高齢でクラウド移行に不安があった。 - 選んだ理由
弥生は従来から利用していたため互換性があり、電話サポートも安心できた。 - 導入後の効果
- サポートの手厚い対応でスムーズに移行。
- 電子帳簿保存法対応が容易になり、ペーパーレス化が進んだ。
- 経理業務を家族で分担でき、属人化を解消できた。
事例から見える傾向
- フリーランス・副業 → 直感的な操作が魅力の「freee会計」が人気。
- 成長期の法人 → 自動化と拡張性に優れる「マネーフォワードクラウド」が選ばれる。
- 長年の利用者・初心者 → サポートが安心できる「弥生会計オンライン」に根強い支持。
クラウド会計ソフトを導入するためのステップ
ステップ1:自社・自分の状況を整理する
- 事業規模(個人事業主か法人か)
- 経理に割ける時間や人員の有無
- 必要な機能(請求書・給与・経費精算など)
👉 例えば「副業ライターならfreee」、「法人化して社員がいるならマネーフォワード」、「初心者で電話サポート必須なら弥生」というように整理します。
ステップ2:無料体験を試す
- freee会計 → 30日間無料トライアル
- マネーフォワードクラウド → 1か月無料お試し
- 弥生会計オンライン → 初年度無料キャンペーン多数
👉 実際に請求書を発行したり、口座連携を試すことで、自分の業務に合うか確認できます。
ステップ3:顧問税理士と相談する
- 税理士によって対応可能なソフトが異なる場合があります。
- 導入前に「どのクラウド会計に対応しているか」を確認すると安心です。
ステップ4:導入後のルールを決める
- 領収書の保存方法(スキャン or 写真)
- 誰が仕訳を入力し、誰が承認するか
- 自動仕訳ルールを定期的に見直すこと
👉 ルールを整えて運用することで、ソフトのメリットを最大限活かせます。
最適なソフトは事業ステージで決まる
- マネーフォワードクラウド会計:自動化・拡張性に優れ、成長期の法人に最適。
- freee会計:直感的な操作が魅力で、初心者やフリーランスに人気。
- 弥生会計オンライン:充実したサポートが強みで、初心者やサポート重視派におすすめ。
👉 2025年に会計ソフトを選ぶなら、「どれが一番安いか」ではなく、**「自分の業務に合うかどうか」**を基準に選ぶことが成功のポイントです。