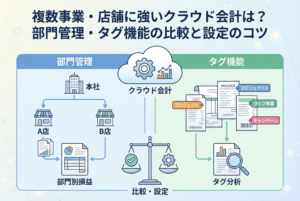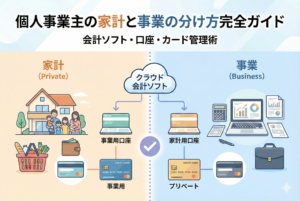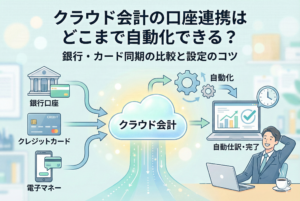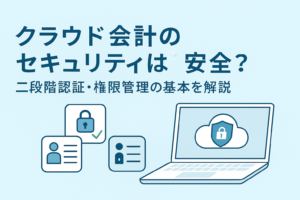会計ソフト選びに迷う個人事業主と中小企業
確定申告や日々の経理を効率化するために欠かせないのが「会計ソフト」です。
特に人気が高いのが、クラウド会計の代表格であるfreeeと、長年の実績を誇る弥生会計オンライン。
どちらも会計ソフトとしての基本機能は備えていますが、操作性やサポート体制、コストなどに違いがあり、利用する人の立場によって「向き・不向き」が変わってきます。
「どっちを選ぶべきか」が分からない理由
多くの事業主が「freeeか弥生、どっちを選べばいいのか」と迷うのは、両者がそれぞれ異なる特徴を持っているからです。
- freeeは「簿記が苦手でも簡単に入力できる」ことを売りにしている
- 弥生は「専門家との連携やサポートが強い」ことで信頼を集めている
一見するとどちらも優れているように見えますが、実際には事業の規模や会計知識、サポートの必要度によって評価が変わります。
会計ソフト選びを誤るリスク
ソフトを選ぶ際に自分に合わないものを導入すると、次のような問題が生じる可能性があります。
- 操作が難しく、結局経理の効率化ができない
- 必要なサポートを受けられず、トラブル時に困る
- コストが割高になり、経費削減につながらない
- 税制改正やインボイス制度への対応で不安が残る
会計ソフトは一度導入すると乗り換えが大変なため、最初に正しく選ぶことが非常に重要です。
freeeが向いている人
初心者や簿記が苦手な個人事業主
- 「簿記の知識がほとんどない」
- 「スマホで簡単に入力したい」
- 「できるだけ自動で仕訳してほしい」
freeeは質問に答えるだけで仕訳が進む直感操作型。
会計初心者や副業で事業を始めた人でも扱いやすい点が強みです。
スマホ中心で経理を完結したい人
- 領収書を撮影して自動仕訳
- 銀行口座やカード明細をリアルタイム同期
- 出先でも申告書の作成まで可能
PCに向かわず、日常の隙間時間で経理を進めたい人におすすめです。
弥生が向いている人
専門家と連携して経理を進めたい中小企業
- 税理士にチェックしてもらいながら記帳したい
- 法人決算や複雑な処理もカバーしたい
- サポートを受けながら安心して利用したい
弥生は税理士・会計士の利用率が最も高く、専門家との相性が抜群です。
法人利用や将来的に事業規模を拡大する予定があるなら、弥生の方が安心です。
電話サポートを重視する人
- 分からないときに直接相談したい
- チャットよりも「人に聞きながら進めたい」
弥生は電話サポート対応が最大の強みで、初心者でも安心して使い続けられます。
freeeと弥生の比較指針
| タイプ | freeeがおすすめ | 弥生がおすすめ |
|---|---|---|
| 会計知識 | 初心者、簿記が苦手 | 簿記の基本は理解している or 専門家併用 |
| 操作スタイル | スマホ中心、直感的操作 | PC中心、従来型操作 |
| サポート | チャット中心、自力で学びたい人 | 電話対応あり、相談しながら進めたい人 |
| コスト | 月額課金型、安定利用 | 初年度無料、翌年以降は年額制 |
| 事業規模 | 個人事業・小規模副業 | 法人、中小企業、将来の拡大を見据える人 |
結論のまとめ
- freee → 「初心者・副業・簿記が苦手な人」におすすめ
- 弥生 → 「専門家併用・法人・中小企業」におすすめ
つまり、
- 自力で簡単に完結したいならfreee
- 専門家と連携して確実に処理したいなら弥生
というのが大きな指針になります。
freeeと弥生の料金比較
会計ソフトを選ぶ際に最も気になるのがコストです。両者の代表的なプランを整理すると以下の通りです。
| ソフト | 主なプラン | 月額(税込) | 年額(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| freee会計 | スタータープラン | 1,628円 | 12,936円 | 青色申告・白色申告に対応、スマホ中心でも利用可能 |
| スタンダードプラン | 2,728円 | 26,136円 | レポート機能・請求書連携強化 | |
| 弥生会計オンライン | セルフプラン | 約1,800円 | 年額12,000円 | 初年度無料、翌年以降も低コスト |
| ベーシックプラン | 約3,000円 | 年額30,000円前後 | 電話サポート・導入支援あり |
💡 まとめ
- freeeは月額課金型で利用しやすいが、長期利用すると割高感がある。
- 弥生は初年度無料・年額制でコストを抑えやすい。
機能面の比較
| 機能 | freee | 弥生 |
|---|---|---|
| 青色申告65万円控除対応 | ○ | ○ |
| 白色申告対応 | ○ | ○ |
| 自動仕訳 | ◎(質問形式で初心者にやさしい) | ○(簿記知識前提で正確) |
| スマホアプリ | ◎(申告まで対応) | △(簡易入力中心) |
| 請求書機能 | 内蔵(freee請求書) | Misocaと連携 |
| レポート分析 | ○(基本的な収支レポート) | △(分析は限定的) |
💡 まとめ
- freeeは初心者向けの自動化・スマホ対応が強み。
- 弥生は専門家と併用する前提で正確な入力・法人決算対応に強い。
サポート体制の比較
| 項目 | freee | 弥生 |
|---|---|---|
| チャットサポート | ○ | ○ |
| メールサポート | ○ | ○ |
| 電話サポート | △(上位プランのみ) | ◎(全プランで対応、特にベーシック) |
| 導入支援 | △(オンラインヘルプ中心) | ◎(電話+オンライン両方あり) |
💡 まとめ
- freeeは「自分で調べながら進めたい人」向け。
- 弥生は「電話で相談しながら安心して進めたい人」向け。
背景にある違い
freeeの設計思想
- 「会計をもっと簡単に」をコンセプトに、簿記知識がない初心者でも使えるようUIを徹底的に工夫。
- 直感的な質問形式やスマホアプリ重視の設計は、副業やフリーランスのニーズにマッチ。
弥生の設計思想
- デスクトップ版からの歴史が長く、税理士や会計士が慣れ親しんでいる。
- 「専門家と連携しながら正確に処理する」スタイルを重視しており、法人や中小企業の利用に強み。
freeeと弥生の利用事例
事例1:フリーランスデザイナー(freee導入)
- 課題:簿記の知識がなく、確定申告のたびに時間を取られていた
- 導入後:領収書をスマホで撮影するだけで仕訳が自動化
- 効果:入力時間が月10時間 → 3時間に短縮。確定申告も自分で完結できるようになった
事例2:小規模飲食店経営者(弥生導入)
- 課題:仕入れや人件費を正確に管理し、税理士とデータ共有したかった
- 導入後:弥生で部門管理を設定し、食材コストや売上を細かく記録
- 効果:税理士とデータを共有することで、決算処理がスムーズに。節税提案も受けやすくなった
事例3:中小企業(従業員15名、弥生導入)
- 課題:法人決算に対応しつつ、経理担当者が初心者でも安心できる環境が必要
- 導入後:電話サポートを利用しながら経理を進め、法人決算も対応
- 効果:経理担当者が短期間で操作を習得。税理士とのやり取りもスムーズに
事例4:副業でEC販売をしている個人(freee導入)
- 課題:複数のネットショップとカード決済の取引が多く、手入力が煩雑
- 導入後:ECサイトやクレジットカードと自動連携
- 効果:入力作業がほぼ自動化され、本業の時間を圧迫しなくなった
freeeと弥生を導入するためのステップ
ステップ1:自分の事業スタイルを確認する
- 簿記に自信がない → freee
- 専門家との連携を重視 → 弥生
ステップ2:無料期間を活用する
- freeeは30日間無料
- 弥生は初年度無料(セルフプラン)
実際に試して「操作の感覚が合うか」を確認しましょう。
ステップ3:銀行口座やカードを連携する
- どちらも金融機関連携に対応
- 連携先の広さで言えばfreeeが有利
ステップ4:入力・仕訳を習慣化する
- 毎月まとめてではなく、こまめに入力
- freeeはスマホアプリ活用、弥生はPC中心で進めると効率的
ステップ5:必要に応じて税理士に相談
- freeeでも弥生でも、最終的な税務判断や節税戦略は専門家の力を借りるのがおすすめ
freeeと弥生、どっちを選ぶべき?まとめ
- freee → 個人事業主、副業、簿記初心者、スマホで簡単に処理したい人
- 弥生 → 中小企業、法人、専門家と連携したい人、電話サポートを重視する人
つまり、
- 簡単・直感的に進めたいならfreee
- 確実・安心を優先するなら弥生
という選び方が最も合理的です。