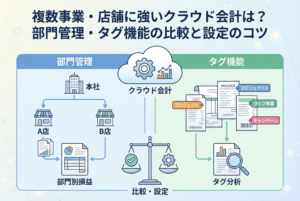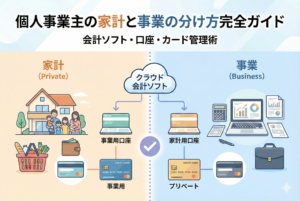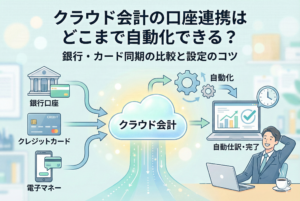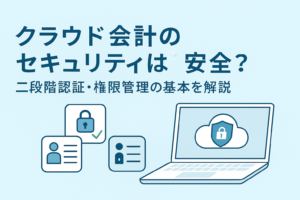目次
弥生会計オンラインとは?
会計ソフトの定番ブランド「弥生」が提供するクラウド型サービスが弥生会計オンラインです。
長年にわたり多くの中小企業・個人事業主に利用されてきた「弥生会計」のノウハウを基盤に、インターネット環境さえあればどこでも使える利便性をプラスしています。
インボイス制度や電子帳簿保存法など、企業を取り巻く会計環境が変化する中で、弥生会計オンラインはクラウド会計ソフトの有力な選択肢として注目されています。
なぜ「メリットとデメリット」を理解する必要があるのか?
会計ソフトは「使えれば何でもいい」と思われがちですが、実際には事業規模や業種、経理体制によって最適なツールは異なります。
もしメリットだけを見て導入すると、以下のような失敗につながることがあります。
- 操作性が合わず、入力に時間がかかる
- サポート体制が期待と違い、解決までに時間がかかる
- 機能が不足していて、事業の拡大に対応できない
- 料金体系が自社の利用状況に合わず、コストが割高になる
逆に、デメリットを理解した上で導入すれば、こうしたリスクを回避し、安心して長期的に利用できます。
本記事の目的と読者へのメリット
この記事では、弥生会計オンラインのメリットとデメリットを体系的に整理し、さらに他のクラウド会計ソフトとの比較も交えて解説します。
対象となる読者は以下のような方です。
- フリーランスや個人事業主で「これから会計ソフトを導入したい」人
- 中小企業経営者で「既存ソフトからクラウドに乗り換えたい」人
- 弥生会計オンラインの導入を検討しているが「本当に自分に合うか確認したい」人
💡 本記事を読むことで、弥生会計オンラインの強みと弱点を理解し、自分の事業に適した選択ができるようになります。
弥生会計オンラインのメリット
1. 長年の実績と信頼性
- 「弥生シリーズ」は30年以上の歴史を持ち、会計ソフト市場でトップシェアを誇るブランド。
- 税理士・会計士の多くが慣れ親しんでおり、専門家とのデータ共有がスムーズ。
2. 初年度無料で導入しやすい
- セルフプランやベーシックプランは初年度無料で利用できるため、初めての導入コストを抑えられる。
- 低リスクで試せるのは、会計ソフト初心者にとって大きな安心材料。
3. 電話サポートが充実
- 他のクラウド会計ソフトはチャット・メールが中心だが、弥生は電話サポート対応が強み。
- 会計初心者でも分からない点をすぐに相談できる。
4. 青色申告・白色申告どちらも対応
- 個人事業主の青色申告65万円控除に対応。
- 白色申告の簡易帳簿作成も可能。
- 法人決算にも利用でき、規模拡大にも対応可能。
5. 税制改正対応のスピード
- インボイス制度、電子帳簿保存法など最新法令への対応が迅速。
- 法改正に不安を感じる事業者も安心。
弥生会計オンラインのデメリット
1. UIがやや従来型
- freeeやマネーフォワードに比べると、画面デザインや操作性が少し古典的。
- 簿記に不慣れな人にとっては直感的に分かりにくい部分もある。
2. 自動連携の範囲が限定的
- 銀行・クレジットカード連携は可能だが、連携先の幅や精度はマネーフォワードに劣る。
- ECやキャッシュレス決済を多用する業種では不便を感じる場合がある。
3. スマホアプリの利便性が限定的
- PC前提で設計されているため、スマホ中心で会計を完結させたい人には不向き。
- 移動中の仕訳や入力を重視する場合、freeeの方が適している。
4. 完全初心者にはややハードルがある
- 簿記用語や仕訳ルールをある程度理解していないとつまずく可能性あり。
- 「質問形式で自動仕訳」が売りのfreeeに比べると、学習コストが必要。
5. プランによってはコストが割高
- 初年度は無料でも、翌年度以降は年額1万〜2万円程度の費用が発生。
- サポート付きプランではさらに費用がかかるため、ランニングコストを考慮する必要がある。
メリット・デメリット一覧表
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 信頼性 | 長年の実績と専門家との相性 | UIが従来型でやや使いにくい |
| コスト | 初年度無料で導入しやすい | 翌年度以降は割高になる場合あり |
| サポート | 電話サポートが充実 | サポート付きプランで追加費用 |
| 機能性 | 青色・白色・法人決算すべて対応 | 自動連携やスマホ機能は弱め |
| 法改正対応 | インボイス・電帳法対応が迅速 | 完全初心者には学習が必要 |
弥生会計オンラインのメリットが生まれる理由
歴史とブランドの信頼性
弥生はデスクトップ版ソフトとして長年利用されてきた実績があります。
- 中小企業や個人事業主から圧倒的な支持を得てきたため、ユーザーのニーズを熟知している。
- 税理士・会計士の多くが弥生に精通しており、専門家にデータを渡してスムーズに処理できる点が強み。
電話サポートが充実している理由
- 他のクラウド会計ソフトは「オンライン完結型」が多いが、弥生はサポート体制を商品価値の一部として明確に位置づけている。
- 会計初心者が電話で直接質問できる仕組みを残していることが、従来ユーザーの安心感につながっている。
法改正対応の速さ
- 長年のシェアを背景に税理士・会計士からのフィードバックが集まりやすく、制度改正への対応力が高い。
- インボイス制度や電子帳簿保存法などの大きな改正にもいち早く対応できたのは、そのユーザー基盤と開発リソースの厚さによるもの。
弥生会計オンラインのデメリットが生まれる理由
UI・操作性の課題
- 弥生会計はもともと簿記知識があるユーザーを前提に作られてきたため、UIも会計用語ベースで設計されている。
- freeeのように「質問形式で自動仕訳」といった初心者向けの工夫が弱く、完全初心者には敷居が高い。
自動連携の弱さ
- マネーフォワードは「資産管理アプリ(マネーフォワードME)」を基盤に連携先を拡大しているが、弥生はこの分野では遅れをとっている。
- 特にECサイトやキャッシュレス決済との自動連携では差がついており、ネットショップ事業者には不向きな面もある。
スマホアプリの制限
- 弥生は「PCでしっかり記帳する」従来型の利用スタイルを重視してきたため、モバイル中心の運用には弱い。
- 外出先での処理や隙間時間の記帳を希望するユーザーにとっては物足りなさを感じやすい。
他社ソフトとの比較(freee・マネーフォワード)
| 項目 | 弥生会計オンライン | freee会計 | マネーフォワードクラウド会計 |
|---|---|---|---|
| 操作性 | 簿記知識がある人向け | 初心者に直感的(質問形式) | 中級者以上に便利、複数連携強い |
| 自動連携 | 銀行・カード中心 | 銀行・カード・請求書・給与まで幅広い | 銀行・カード・EC・電子マネーなど最多 |
| サポート | 電話サポートあり | チャット中心 | チャット・メール中心 |
| コスト | 初年度無料、翌年度年額制 | 月額課金(約1,300〜) | 月額課金(約1,400〜) |
| 専門家連携 | ◎税理士との相性抜群 | △利用専門家少なめ | ○徐々に普及中 |
| モバイル性 | △スマホ機能は限定的 | ◎スマホ完結可能 | ◎スマホアプリ充実 |
💡 まとめ
- 弥生 → 専門家連携・サポート重視
- freee → 初心者向け・スマホ中心
- マネーフォワード → 複数収入源や自動連携を活用する人向け
弥生会計オンラインの活用事例
事例1:飲食店オーナーAさん
- 課題:毎日の現金売上とカード決済の突合に時間がかかっていた
- 導入後:銀行口座とカードの自動連携を利用し、売上データを効率的に取り込み
- 効果:仕訳作業が月20時間から5時間に短縮、空いた時間をメニュー開発に活用
事例2:建設業経営者Bさん
- 課題:工事ごとの原価管理をエクセルで行っており、数字が煩雑に
- 導入後:部門管理機能を使い、工事別に材料費・人件費を記録
- 効果:赤字工事を早期に把握でき、見積もり精度が向上
事例3:税理士と顧問契約を結ぶ士業Cさん
- 課題:顧問契約の請求や月次データのやり取りに時間がかかっていた
- 導入後:弥生データを税理士と直接共有
- 効果:やり取りがスムーズになり、申告業務にかかる日数を削減
弥生会計オンライン導入のステップ
ステップ1:プランを選ぶ
- セルフプラン:自分で記帳・申告を行いたい人向け
- ベーシックプラン:サポート重視、電話相談を利用したい人向け
ステップ2:初年度無料で試す
- まずは初年度無料キャンペーンを活用して、実際の操作感を確認する
- freeeやマネーフォワードと比較して、自分に合うか判断
ステップ3:金融機関・カードを連携
- 銀行口座やクレジットカードを登録して自動仕訳を有効化
- 手入力を最小限に抑えて効率化
ステップ4:月次処理を習慣化
- 毎月1回は必ず数字を確認
- 損益や資金繰りを把握し、経営判断に活かす
ステップ5:必要に応じて税理士と併用
- 自分で仕訳・帳簿付けは可能でも、節税戦略や税務判断は専門家に相談
- 弥生会計は税理士の利用率が高いため、併用がスムーズ
弥生会計オンラインを選ぶべき人まとめ
- 税理士と併用して確実な会計処理を行いたい人
- 電話サポートを利用して安心したい初心者
- 工事原価や複雑な会計処理に対応したい中小企業
- 初年度無料で試したいコスト重視の個人事業主
逆に、スマホ中心で手軽に処理したい人や、EC連携を重視する人にはfreeeやマネーフォワードの方が合うケースもあります。